厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改訂や副業マッチングサービスの増加など「副業」を取り囲む環境が急速に変化しており、企業・個人ともに副業への取り組みが積極化し始めている。
企業と個人が1:1の関係から多:多のMany to Manyへと移行する時代に、企業が意識すべきポイントはどこにあるのだろうか。
今回は「副業に関する現実」「副業が広まる要因」「副業のメリット・デメリット」「企業に求められる対策」そして「複業時代のM2M採用と企業意識改革」という切り口で述べてみたい。
副業についての現実
副業の容認に関する調査結果が公開された。
2021年8月16日にパーソル総合研究所が行った「第二回 副業の実態・意識に関する定量調査」(※1)は従業員10名以上の経営層や人事と34,000名以上の個人をスクリーニング対象とした調査を行っている。
データによると、副業を全面的に容認する企業の割合は23.7%、条件付きで容認する企業の割合が31.3%で、合計で55.0%の企業が「副業を認める」と回答している。
2018年の調査では51.2%であったことから、副業を容認する企業の割合はやや増加したと言え、パーソル総合研究所では「企業において副業が一般的なものとして認識されつつある」と分析している。
一方、2021年9月1日に全国の総務担当者に対して実施した「月間総務」の「副業に関する調査」(※2)によると、副業制度があると回答している企業の割合が19.4%、副業制度はないが黙認しているという企業が9.7%と計29.1%にとどまっている。
経営層・人事の55%が「副業を認める」としている一方、総務担当者のそれが29.1%にとどまっているのは労働時間の通算が必要な雇用契約に基づく副業のみを対象としているからである可能性がある。
しかし、実際には雇用契約ではなく業務請負契約に基づく事実上の副業も少なくない。東京新聞は2020年7月に「低賃金で不安定な働き手を増やす恐れもはらむ」として警鐘を鳴らしている(※3)。
こうした点を踏まえれば、副業の容認に関する実態は経営者や人事を対象にした55.0%の方が近いのではないかと考える。
副業を行っている個人の割合はパーソル総合研究所によると9.3%で、2018年調査時の10.9%と比較すると低下している。
意外な気もするが、これは新型コロナ禍で「飲食業の休業や営業時間短縮などにより、パート・アルバイトで働く副業者の受け皿が減少した」からであると言う。
副業の意向がある個人の割合は40.2%であることから、かなりの人々が副業をしたいと考えている現状が窺えるが、専門的なスキルを持つ人材に偏っているとみられ、現実的には副業に踏み込めていない人が多数であり、一部の高度人材に留まっているのが現状と言えよう。
副業が広まる要因
既に副業に取り組んでいる人の割合は10%程度に過ぎないが、企業の過半数が既に副業を容認しており半数近くが副業の受け入れに対し前向きな姿勢を示していること、それに個人の40%が副業したいという意向であることから、一層の普及は時間の問題だ。
また、副業の普及をさらに加速させるであろう要素も整いつつある。ここでは今後副業の一般化に弾みがつくであろう環境要因について述べていく。
副業について企業・個人の意識変化に最も大きな影響を与えたのは2018年に策定され2020年に改訂された厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(※4)であろう。
基本的な考え方として「原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である」とされており、企業に副業を促進するための対応を求めているのだ。
このガイドラインを受けて企業側の取り組みが本格化したが、それだけではない。
副業をマッチングするサービスが次々と生まれ利用が拡大している。日本経済新聞社のスキルシェアサービス「NIKKEI SEEKS(※5)」やBETAではあるが「Yahoo!JAPAN副業(※6)」など大手も参入していることを見れば明らかだろう。
また既存のランサーズやクラウドワークスといったクラウドソーシングサイトが副業探しの受け皿として進化している点も見逃せない。
さらにWantedlyやEightなどビジネスSNSが副業による人材募集ツールの役割を果たし始めている。
Wantedly(※7)では「副業」の募集を検索できるほか、Eightでは登録者がプロフィールに「複業・兼業」の名刺登録が可能となるなど対応が進んでいるのである(※8)。
厚生労働省のガイドライン改訂を背景に、副業マッチングサービスの登場やクラウドソーシングサイト・ビジネスSNSの進化を環境要因として拡大している形だが、副業の普及を加速させている環境要因は他にもある。
新型コロナ禍における収入減とリモートワークの急速な利用増だ。
特にZoomに代表されるミーティングアプリとSlack、ChatWorkといったコミュニケーションツールは業務のあり方を大きく変えており、自宅で仕事というスタイルを定着させた。
これらの理由から副業の活用は企業・個人の双方に広がりを見せているのである。
副業のメリット・デメリット
副業についての現在の状況は
・ビジネス感度の高い企業が高スキルのプロフェッショナル人材を有効活用し始めている
・個人が副業マッチングサービスやビジネスSNS、クラウドソーシングサイトに登録し複数の企業と接点を持ち始めている
と言えるが、では企業・個人にとって副業にはどんなメリット及びデメリットがあるのだろうか。
副業人材を受け入れる企業にとっては、自社に不足しているスキルの活用や人件費の抑制、従業員の負担軽減といった効果に加え、外部の人材が持つスキルが既存従業員にとっての刺激になるというメリットがある。
一方、自社社員の副業を認める企業にとっては視野の拡大や新たな分野への挑戦に対する抵抗感の減少などを理由に「副業者の3~4割が、副業をしたことで本業にプラスの変化があった」と回答(パーソル総合研究所調査)していることから、こうした効果をメリットとして挙げることができる。
個人にとって副業がもたらすメリットとしては収入の増加やキャリア形成、スキルの向上そして人脈の広がりなどがある。
では、企業・個人にとってのデメリットとしてはどんな点があるのだろうか。
副業人材を受け入れる企業にとっては社内情報の流出リスクや社内秩序の混乱、それに煩雑化する労務管理といった点が、また副業を認める企業にといっては副業先に転職されてしまうリスクや顧客リストの流用リスク、それに副業を理由とする残業拒否といった点がデメリットとなる。
個人にとっては副業の業務がもたらす過重労働の危険性が何よりのデメリットであろう。
企業に求められる対策
企業が副業の受け入れや容認に踏み切る際には、どのような対策を講じておくべきなのだろうか。
副業を受け入れる企業に求められる対策としては「待遇制度」「守秘義務」から考える必要がある。
待遇制度としては副業人材の勤務時間や勤務地の管理や賃金に関する規定、それに交通費や通信費の支給有無や業務で使用するPC・スマホの貸与について定めておく必要がある。
特にリモートワークの普及で自宅などオフィス外勤務が当たり前になっていることから、待遇制度のきめ細かい設定は重要であると言える。
また守秘義務契約は前項で述べた通り社内情報の流出リスクがあるため、副業人材との間で必ず交わしておくべきである。
次に副業を認める企業に求められる対策としてはまず副業を認める要件の設定を挙げることができる。
これは労働基準法第38条1項が「自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要がある。」と定めている通り副業先における勤務時間まで把握することが求められているためで、他にも厚生労働省のガイドラインでは企業に対し健康管理も適切に行う必要がある。
厚生労働省のガイドラインでは企業側が留意すべきポイントとして次の5つが挙げられている。
・安全配慮義務
・秘密保持義務
・競業避止義務
・誠実義務
・副業・兼業の禁止又は制限
そのため、守秘義務契約やストレスチェックなどの健康管理はもちろん、副業先企業での業務が競業とならないかどうか、労働時間通算の対象となるか否か、自社の名誉や信用を毀損しないかといった点について把握するために副業を認める要件を設定しておく必要があるのである。
複業時代のM2M採用と企業意識改革
副業の一般化によって企業と個人の関係性が大きく変化している。
企業と個人が1:1であったこれまでの関係は、企業が副業人材を活用し個人が複数の企業と契約を結ぶ多:多、つまりMany to Many(M2M)の関係に移行しつつあるのである
M2M時代に企業が採用において意識すべきポイントは大きく2つである。
まずジョブ型雇用への対応能力を高めておくこと。
もちろんこれまでの新卒一括採用に代表されるメンバーシップ型雇用の重要性は変わらない。
だが、副業の普及以前から本格化している中途採用におけるジョブ型雇用に高度対応できている企業はまだ多いとは言えない。
求人広告や人材紹介以外の存在感を高めている採用手法であるダイレクトリクルーティング、それにいくつものサービスが登場している採用広報を本格的に活用していると言える企業はまだ少数派だ。
さらに最近ではリファラル採用を制度化する動きがみられており、これら複数の採用手法と社内で細分化を続ける職種それぞれに対応する採用フローを準備するなど採用活動で求められる俯瞰化には到底手が届いていないという企業が多いだろう。
M2M時代には必要なスキルを持つターゲット人材を短時間で見分けることができるだけのジョブ型雇用への対応能力を企業側が持っておくべきなのである。
もうひとつのポイントは「ムラ社会からの脱却」を企業側が意識しておくことだ。
ムラ社会とは独自の秩序とルールを設け外部を受け入れない排他的な社会であり、何より重視されるのが調和であるという特徴を持っている。
似た価値観に支配されるムラ社会は変化に弱く自分たちの論理に合致しない者を排除しがちであることから、このような企業では外部の優秀な副業人材がスキルを活かすことが難しいのである。
特にリモートワークにより対面で仕事をする時間が少ない副業人材は、企業側による非生産的な業務プロセスの押し付けなどあった場合、すぐに離職してしまいかねない。
採用担当者はこの点についても十分に意識した上でM2Mを前提とした採用活動を実施すべきなのである。
参考URL:
※1:【パーソル総合研究所】第二回 副業の実態・意識に関する定量調査
https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/research/activity/data/sidejob2.html
※2:【月間総務】副業に関する調査
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000060066.html
※3:【東京新聞】<働き方改革の死角>副業・兼業の「労働時間の通算」問題決着 課題は低賃金で不安定な働き手を増やす恐れ
https://www.tokyo-np.co.jp/article/39726
※4:【厚生労働省】副業・兼業の促進に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf
※5:NIKKEI SEEKS
https://seeks.nikkei.com/
※6:Yahoo!JAPAN副業BETA
https://sidejob.yahoo.co.jp/
※7:Wantedly
https://www.wantedly.com/
※8:【Sansan】Eight、プロフィールに複業・兼務の名刺登録が可能に~増加する複業ニーズに対応~
https://jp.corp-sansan.com/news/2020/eight_v9-5_update.html










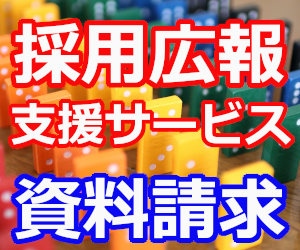 "
"








 "
"
